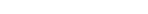ユーラシア大陸のほぼ北半分を占めると言っても過言ではない、広大な国土を誇るロシア。この世界一大きな国が、まだソヴィエト連邦と呼ばれていた時代、この地に人類史上最悪ともいうべきシリアルキラー(連続殺人犯)が出現した。当局の「連続殺人は資本主義の弊害によるもの。社会主義下のわが国家に、この種の犯罪は存在しない」という公式見解も災いして、事件の捜査は遅々として進まず。結局犯人逮捕までには12年という歳月を要し、その間の犠牲者は判っているだけでも52人に及ぶという大事件となった。
ユーラシア大陸のほぼ北半分を占めると言っても過言ではない、広大な国土を誇るロシア。この世界一大きな国が、まだソヴィエト連邦と呼ばれていた時代、この地に人類史上最悪ともいうべきシリアルキラー(連続殺人犯)が出現した。当局の「連続殺人は資本主義の弊害によるもの。社会主義下のわが国家に、この種の犯罪は存在しない」という公式見解も災いして、事件の捜査は遅々として進まず。結局犯人逮捕までには12年という歳月を要し、その間の犠牲者は判っているだけでも52人に及ぶという大事件となった。
1992年4月になって、〈ニューヨークタイムズ〉がこれを報じ、ニュースは駆け巡り世界中を震撼させたが、2008年、ロシアの大地に眠るこの前世紀の忌まわしい記憶を、小説という形で揺り起こそうとする作家が登場した。イギリスのトム・ロブ・スミスである。
陰謀により国家保安省を追われ、民警へと左遷されたエリート捜査官が、赴任先の田舎町で連続殺人事件に遭遇する「チャイルド44」は、英語圏最高のミステリ賞のひとつ、CWA(英国推理作家協会)がその年のもっとも優れたスリラー小説に授ける〝イアン・フレミング・スチール・ダガー賞〟を射止めると、いちはやく日本にも翻訳紹介された。〈このミステリーがすごい!〉の海外部門で1位に輝いたのをはじめとして、この新鋭のデビュー作がわが読書界を席巻したのは、まだ記憶に新しいところといえる。
言うまでもなく映画『チャイルド44 森に消えた子供たち』は、このトム・ロブ・スミスのベストセラー小説を原作としているが、実は映画化のニュースが舞い込んできた当初は、一抹の不安もあった。というのも、テレビ局で自身のキャリアをスタートさせた作者は、かつて映像の世界でロシアという舞台を取り上げることの困難さについて語っていたからだ。そもそも、「チャイルド44」を書いた理由が、この国が抱える社会的な問題や、歴史的な背景は、小説でこそ表現しうると考えたことがきっかけだったという。
しかし映画界から名乗りをあげたのが、歴史劇からSFまで作品毎に多様な世界観を打ち立ててきた巨匠リドリー・スコットであったことが、そんな危惧を吹き飛ばしてくれた。やがて彼は製作にまわり、メガホンを取るのは『イージーマネー』、『デンジャラス・ラン』のダニエル・エスピノーサであるとアナウンスされたが、この北欧スウェーデン生まれの俊英の抜擢が誤りでなかったことは、全体主義のユートピアを裏側から眺めた犯罪スリラーという前代未聞の原作を、少しもブレることなく映像作品に仕上げた手腕からも明らかだろう。
 事件を追う捜査官のレオ・デミドフは、実は妻ライーサとの関係にも危機的な状況を抱えている。連続殺人の捜査と並行して描かれるのは、そんなレオとライーサが互いの信頼を回復するまでの濃やかなドラマだ。その過程を巧みに織り込んだ脚本は、「フリーダムランド」や「黄金の街」でおなじみ、エンタテインメント文学との二足の草鞋で活躍するリチャード・プライスによるもので、トム・ハーディ演じるレオの心根の優しさや、ノオミ・ラパス演じる妻ライーサの芯の強さ、さらには彼らとゲイリー・オールドマン演じる頑固な警察署長ネステロフの間に芽生える協力関係などを次々に描き出していく。
事件を追う捜査官のレオ・デミドフは、実は妻ライーサとの関係にも危機的な状況を抱えている。連続殺人の捜査と並行して描かれるのは、そんなレオとライーサが互いの信頼を回復するまでの濃やかなドラマだ。その過程を巧みに織り込んだ脚本は、「フリーダムランド」や「黄金の街」でおなじみ、エンタテインメント文学との二足の草鞋で活躍するリチャード・プライスによるもので、トム・ハーディ演じるレオの心根の優しさや、ノオミ・ラパス演じる妻ライーサの芯の強さ、さらには彼らとゲイリー・オールドマン演じる頑固な警察署長ネステロフの間に芽生える協力関係などを次々に描き出していく。
ところで、「チャイルド44」の原作者トム・ロブ・スミスが執筆にあたり影響を受けたのが、ロバート・カレンの「子供たちは森に消えた」であることは間違いない。〈ニューズウィーク〉のモスクワ支局長も務めた著者によるこのノンフィクションから立ち上がってくるのは、「チャイルド44」の犯人のモデルとなった連続殺人犯アンドレイ・チカチーロの生々しい姿である。
チカチーロという常軌を逸した大量殺人犯がウクライナに現れた理由は、映画の冒頭にもある1930年代にホロドモール大飢饉がもたらした壮絶な飢餓や、母親の虐待が遠因であったと考えられる。しかし、子どもや女性ばかりを残虐な手口で弄び、殺害するという悪魔的な所業とは裏腹に、穏やかで温厚な一面も有していたという。
今回の映画化で注目したいのは、禍々しい犯行を重ねる男と、それを追う民警の捜査官のスリリングな対決とともに、世紀のシリアルキラーを単なるモンスターと片付けるのではなく、そのプロフィールを克明に描いてみせたところだ。このように、犯人の実像をリアルに捉えたことが、『チャイルド44 森に消えた子供たち』という映画を、すぐれた原作から、さらに進化させた秘密といえるかもしれない。
映画は、事件の解決とともに、レオとその家族の新たな歴史が始まることを暗示していったん幕が降りる。しかし、この原作を発禁処分にしたロシアは、社会主義という重圧が正義をも歪めたという事実を今も認めていない。ペレストロイカを経てもなお、チェチェン紛争や昨今のクリミア情勢など、かの国をめぐる火種は絶えることがないが、そんなロシアがたどる命運を、デミドフ一家のその後とともに描く3部作の残る2作(『グラーグ57』、『エージェント6』)も、引き続き映画化が望まれる。